ここに書くのは、若年性認知症の家族を支える人が、日々どんな大変さを抱えているのかを知っていただくためです。
というのも、若年性認知症の方は一見元気でADL(生活動作)が自立しているように見えるため、**「大きな援助はいらない」**と誤解されてしまうことが多いからです。
でも実際には、家族は毎日、断続的にサポートを続けています。
どんなことをしているのかを少しでも知ってもらい、周りの方が理解や支援を考えるきっかけになれば嬉しく思います。
◆ 「怒ってしまう」その裏にあるもの
時々、認知症の方に対して怒っている家族を見かけることがありますね。
「もっと優しくできたらいいのに」と思う方もいるかもしれません。
でも、そう簡単なことではないんです。
たとえば、うちの場合――
「最近、、、最近、、、最近、、、えーと、最近~、、、(しばらく続く)」
というふうに、ひとつの言葉を出すまでにすごく時間がかかることがあります。
最初のうちは我慢できるんです。でも、何度も「最近、、、最近、、、」と繰り返されると、聞いている側の頭の中もぐるぐるしてきて、つい叫びたくなる。
わたしはつい言ってしまいました。
「ごめん、もう『最近』って言わないで…きつい😓」
「ヤシさんがしたこと?食べたこと?聞いたこと?」
「えっと、最近〜、、、最近、、、」
「(きゃああああ〜😭)」
……こういう時、どれだけの葛藤と我慢があるか、経験した人ならわかると思います。
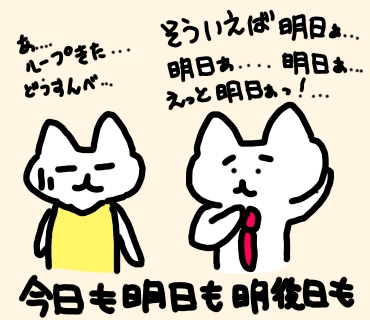
もちろん、「怒ってしまうこと」を正当化したいわけではありません。
できるだけキレないように工夫もしますし、事前に防ぐ努力もしています。
それでも、どうしても耐えられなくなる瞬間があるんです。
そしてそのあと、後悔して泣きたくなる。
◆ 思い出すのは、あの頃の叔父の姿
そんなとき、よく思い出すのが、認知症の祖母を介護していた叔父の姿です。
叔父はよく祖母にどなっていました。でもその一方で、美容院に連れて行き、お寿司をごちそうし、喜ばせようと一生懸命でした。
その“両極端”が昔は理解できませんでしたが、今は痛いほど分かります。
もどかしくて、悔しくて、認めたくなくて、怖くて――どうしようもなくなる時があるんです。
◆ 「怒り」は経過ではなく、結果
あるとき聞いた言葉があります。
「怒ってしまうのは経過ではなく、もう結果。」
つまり、**怒りはそれまでの努力や関係を一瞬で壊してしまう“結果”**なんですよね。
怒った後には、後悔や自己嫌悪ばかりが残ります。
だからこそ、最近は「ダメだ」と思ったら、早めに諦めるようにしています。
もちろん、伝え方を工夫したり、別の表現を試したりもします。
でも、3回やってだめなら切り替える。
本人の頭の中は、同じ言葉がぐるぐるしている状態です。
無理に踏ん張っても出てこない。
ちょっと変な例えかもしれませんが――便秘と同じで、無理に出そうとしても出ない時はある。
気分を変えて水を飲んだり体を動かしたりすると、すっと出ることもありますよね。
それくらいの“切り替え”が大事なんだと思います。
◆ とにかく「待つ」時間の多さ
認知症の家族を支える中で、一番多いのは「待つ時間」です。
- 言葉が出るのを待つ:物の名前や表現がすぐに出てこないため、短い会話にも時間がかかります。
- 理解するのを待つ:説明しても、本人の中で整理されるまでに時間がかかるので、何度もゆっくり確認する必要があります。
- 自分でやりとげるのを待つ:動作や判断がゆっくりになるため、つい手を出したくなりますが、本人が達成感を得られるように見守る時間も必要です。
この「待つ力」が、いちばん試されるのかもしれません。
◆ 周りの目と、心の揺れ
もう一つつらいのは、外での周囲の目です。
変わった言動をしたとき、恥ずかしさやもどかしさが押し寄せます。
何よりショックなのは、「その一瞬だけ」を切り取って見られてしまうこと。
「本当はこんな人じゃないのに」と思う気持ち。
高齢でも子どもでもない、まだリーダー的な年齢の男性が、戸惑ったり迷ったりする姿は、家族としても受け入れがたい瞬間があります。
家の中ならまだしも、外では“しっかりした姿でいてほしい”という願望があるからこそ、ギャップにショックを受けることもあります。

◆ 生活の中の小さな「無駄」と「手間」
空間認識の低下や手先の不器用さから、ものを落としたり、こぼしたりすることが増えます。
子どもがソフトクリームを丸ごと落としてしまうような、そんな場面が日常の中に何度も起きます。
そのたびに掃除をし、片付けをし、時間や手間がかかる。
それもまた、静かなストレスのひとつです。
◆ 1人で2人分を考える日々
家族は、自分自身の生活に加えて、認知症の家族のスケジュールを把握し、的確に動けるようにサポートします。
声かけや見守り、ちょっとした促しも必要。病院などは予約から診察まで付き添います。
子育てに少し似ているかもしれません。
でも子育てと違うのは、「できることが増えていく」のではなく、「できることが減っていく」こと。
その現実に向き合うのは、正直とてもつらいです。
今はまだ1人でサポートできているけれど、これから先はどうなるのか――
そんな不安を、毎日どこかで感じながら過ごしています。
◆ 心配の連続
なるべく本人の自立につながるように、少しでも症状が悪化しないように、**「自分でできることは自分でやる」**を大切にしています。
でも一方で、いつもと違うことをお願いするときには、つい耳を澄まし、様子をうかがい、「大丈夫かな」と心配してしまいます。
特に本人が自分から離れているときは、
「きちんとできているだろうか」「困っていないだろうか」「周りに迷惑をかけていないだろうか」と、心が落ち着きません。
外出前は、時間を守れるように声をかけ、身だしなみを促し、忘れ物をチェック。
一緒に確認して送り出し、待ち合わせ場所を間違えていないかまで気になります。
きっとそのうち、待ち合わせ場所まで送っていくようになるんでしょうね。
心配しすぎても仕方がないとは分かっています。
でも、「またやっちゃった」と本人が落ち込まないように、できる限りサポートしたい。
そういう意味では、デイサービスやデイケアなど、専門職の方々にお任せできる時間はとてもありがたいです。
それでも、うちではこれまで築いてきた関係を大切に、できるうちは仲間たちの手を借りながら、楽しい時間を作っていきたいと思っています。
◆ おわりに
認知症の家族を支えるということは、「待つ」「受け止める」「切り替える」、そして「心配しながら見守る」の繰り返しです。
その中にある怒りも涙も、愛情の裏返し。
完璧じゃなくていい。
キレてしまう日があっても、心配しすぎて疲れてしまっても、また立ち直れたらそれでいい。
同じように頑張っている誰かの心が、少しでも軽くなればと思って書きました。
関連記事はこちら
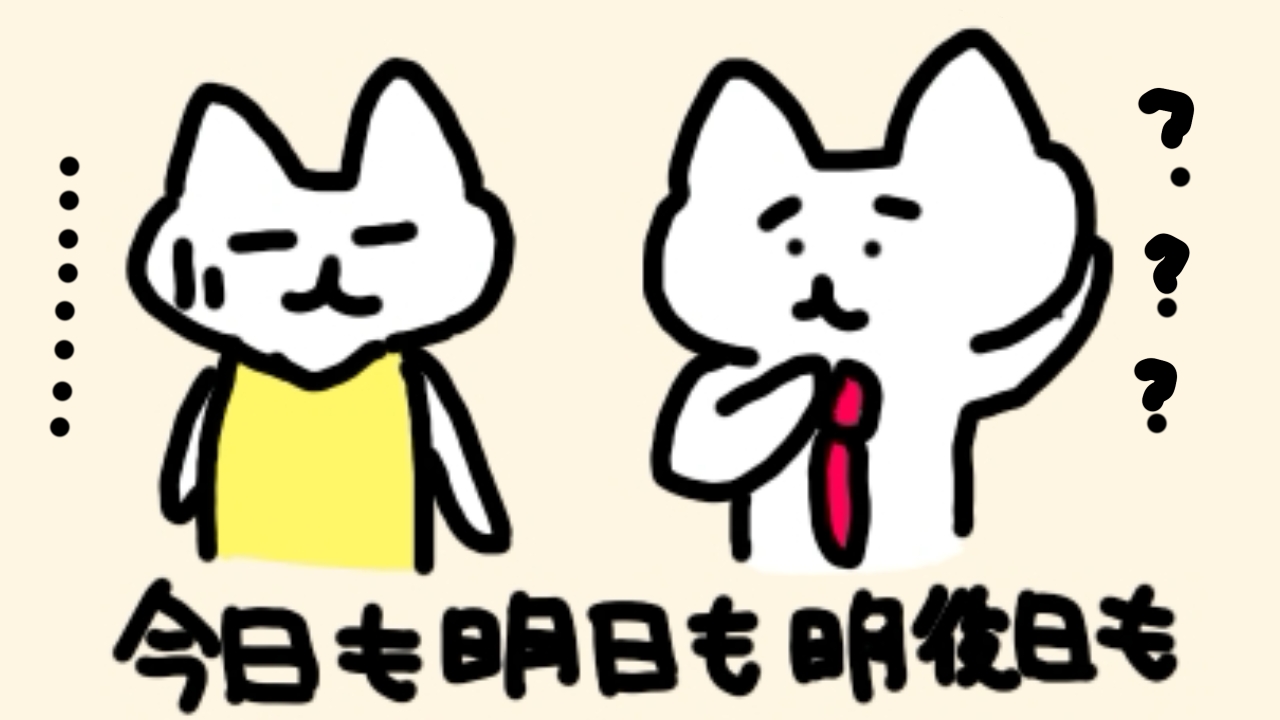


コメント