高齢者や病気の家族を支える中で、本人だけでなく支える側のケアも大切です。
高校時代の訪問看護実習での体験と、現在自分が介護者・支えられる立場になった今の気持ちを通して、学んだことをシェアします。
高校時代の訪問看護同行で見た光景
介護実習で、訪問看護に同行したときのこと、ある高齢のご夫婦の家を訪れました。
そこは奥様が寝たきりで、ご主人が介護をしておられるおうちでした。
部屋に入ってすぐ、看護師さんが「〇〇さん、おでこどうしたの〜?」と声をかけました。
寝たきりの奥様のおでこには、大きな紫色のあざがあったからです。
それは生まれつきのものかと思うほど、丸くはっきりとしたあざでした。
でも、ご主人がすぐに答えました。
「ああ、それはオレが懐中電灯で殴ったんだよ!こいつが“水が飲みたい”ってうるさいからよ!」
その荒くとがった声と衝撃の告白に、私は頭が真っ白になり、震えました。
流石の看護師さんは、落ち着いてていねいに対応していましたが、私は涙が出そうになり、実習が終わるころには心がぐちゃぐちゃでした。

先生に教わった「理由を考える視点」
その日のうちに学校に戻り、わたしは介護を教えてくれていたY先生に話をしました。
先生は私の話を聞いたあと、こう尋ねました。
「あなたはどうしてそのおじいさんが『水を飲みたい』っていう奥さんに怒ったと思う?」
「え、、、」
そんなの、ひどい人だからに決まってる、、、と思っていた私は、答えられませんでした。
すると先生が続けて聞きました。
「水を飲んだら、そのあと身体に入っていってどうなる?」
「、、、トイレに行きたくなる?」
「じゃあ、そのあとおじいさんはどうしなきゃいけない?」
、、、オムツ交換。
その瞬間、ハッとしました。
おじいさんは、毎日毎日、奥さんの食事を作り、食べさせ、片付け、休む間もなく排泄介助をし、また「水が欲しい」と言われる。
その積み重ねが、怒りと疲れとなって噴き出したのかもしれない——。
支える人の苦労と自分の気持ち
もちろん暴力は決して許されません。
けれど、私は“かわいそうな奥さん”と“ひどいおじいさん”という単純な構図でしか見られなかったのです。
一方で、看護師さんや先生は「なぜそうなったのか」を考え、そこから「どう支援できるか」を探っていました。
あの時の衝撃が、今の私の原点です。
「支える人のケア」がどれほど大切かを、私はその日から考えるようになりました。
そして今、私は“介護をする側”になりました。
できることとできないこと、優先順位、体力と気力のバランス——。
その現実を、日々痛いほど感じています。
周りのアドバイスと自分の限界
最近、友人に「もっとやってもらったほうがいい」「先回りせず、失敗させてもいい」と言われました。
その言葉の優しさもわかります。
でもその時、私はつい口にしてしまいました。
「私にも限界がある」
できるときはできる。
でも、すべてを犠牲にして支えることはできない。
余力がある時、待てる時、そんな条件の中で、私はできる範囲のことをしているだけなんです。
そうしないと、私自身が壊れてしまうから。
だから私はときどき言います。
「悪いけど、今は私にやらせてね」
ヤシさん(夫)が自分でやりたそうな時でも、急いでいるときはそう声をかけます。
最初は待てても、結果的に怒ってしまったら、悲しいだけだから。
支える人のケアの大切さ
たくさん失敗して、いまのバランスを見つけてきました。
きっとこれからも、そのバランスは少しずつ変わっていくと思います。
だから、どうか周りの人には知ってほしい。
「なぜそうしているのか」を、まず聞いてほしい。
その人が何も考えずにしているのか、理由があってそうしているのか。
見た目だけでは分からない背景があるのです。
信じてもらえていないと感じると、本当に悲しくて苦しい。
そして——本人を支える家族のケアも、もっと大切にしてほしい。
本人だけを支えるケアでは、良い循環は生まれません。
支える人も、支えられる人も、どちらも「ひとりの人」として見てほしい。
あの日に学んだことが、今、自分が支えられる立場になって、より切実に、そして身近に感じられています。
関連記事はこちら👉若年性認知症の夫を支える日々 怒ってしまう家族のリアルな気持ち


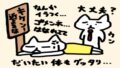
コメント